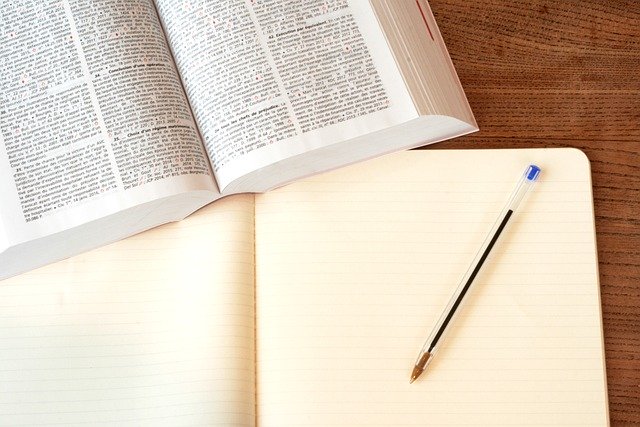
2020年、あるいは2021年に施行される同一労働同一賃金ですが、あなたはどのくらい把握しているでしょうか。
多くの場合は「非正規雇用者も正社員と同じ待遇をしなければならない」といった風に捉えているかもしれません。
しかし、実際にはもっとさまざまな見直しが必要になります。
具体的な内容を把握していないと、同一労働同一賃金によって訴訟のトラブルが発生する可能性もあります。
そうならないためにも、同一労働同一賃金について学びましょう。
まずは、基本的なおさらいからです。
同一労働同一賃金とは
同一労働同一賃金とは、働き方改革の一つです。
内容は、作業時間や内容などの条件が一緒の労働をしている場合、雇用形態や年齢、性別などによって給与や待遇に差をつけてはいけないという法律です。
例えば正社員とアルバイトが同じ業務をしているのに、正社員は月給20万に対し、アルバイトが15万円といった格差が生じている場合、正社員の給料を下げるか、アルバイトの給料を上げる必要があるということです。
給料以外にも、福利厚生も同一にしなければならないので、給料の差額以外にも保険や交通費なども確認しなければなりません。
また、正社員同士でも本社からの出向社員と子会社の社員で同じ労働内容で賃金格差が生じている場合も、状況によっては同一労働同一賃金似抵触する可能性があります。
いつごろ施行されるか
同一労働同一賃金が施行されるのは、大企業の場合2020年4月、中小企業の場合は2021年4月です。
つまり、中小企業の場合は体制を整えるのに一年の猶予があるということです。
ここで注意したいのは、時間に余裕があるからと対策を後回しにすると間に合わなくなるということです。
もし、自社で同一労働同一賃金にて移植している項目があった場合、その項目を修正しなければなりません。
しかし、その修正によって従業員の業務内容や給与内容などに変化が生じ、会社が円滑に機能しなくなる恐れがあります。
したがって、同一労働同一賃金のチェックや会社の制度の見直しは、できるだけ余裕を持って行なうのがオススメです。
厚生労働省の窓口の無料相談や、プロのコンサルタントと相談し、早めに対策を練りましょう。
大企業と中小企業
上で書きましたが、大企業の場合は2020年、中小企業の場合は2021年施行です。
ここで気になるのは、大企業と中小企業の定義です。
厚生労働省では、中小企業の定義を「資本金の額または出資の総額が一定額以下の場合、または常時使用する労働者数が一定以下の場合」と定めています。
これは、業種内容によって数字が変動します。
例えばサービス業や小売業の場合、資本金もしくは出資の総額は5000万円以下が条件なのに対し、製造業や運輸業の場合は3億円以下と定められています。
従業員数もサービス業は100人以下、小売業の場合は50人以下と区分されているので該当するかどうかは厚生労働省できちんと確認しましょう。
罰則について
そんな同一労働同一賃金ですが、現状違反しても罰則がありません。
というのも、厚生労働省では同一労働同一賃金による罰則を定めていないからです。
よって、極端にいえば同一労働同一賃金を守らなくても罰金の支払いなどは現状生じません。
しかし、あくまでも「現状は」であり、2020年、あるいは2021年頃に罰則が制定される可能性があるので注意しましょう。
また、違反している場合は警告を受け、それでも是正されなかった場合は公表される恐れがありますし、従業員から訴えられるケースもあります。
その場合、企業イメージは著しく悪化するので、リスクのほうが遥かに大きいと考えて良いでしょう。
ルールを守って会社を成長
以上、同一労働同一賃金の基本的なお話でした。
ここで紹介したのはあくまでも基本的なおさらいであり、企業によって対策方法は大きく変わります。
また、問題があった場合の対処で会社の内情が悪化する恐れもあるので、早めのうちに専門家に相談するなどの対策を練りましょう。